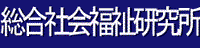
総合社会福祉研究所 > 社会科学・社会福祉基礎講座 > 第12回社会科学・福祉基礎講座 > 第12回社会科学・福祉基礎講座 8A回レジュメ(抜すい)
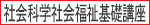
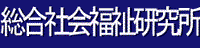
|
社会科学・社会福祉基礎講座
総合社会福祉研究所 > 社会科学・社会福祉基礎講座 > 第12回社会科学・福祉基礎講座 > 第12回社会科学・福祉基礎講座 8A回レジュメ(抜すい) |
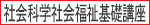
|
第12回社会科学・福祉基礎講座 8A回レジュメ(抜すい)
生活をとらえる視点 浜岡政好(佛教大学)
Ⅰ.生活をとらえるための理論編
1.複雑な生活にどう迫ったらいいのか?
1)まず、いまの次代の社会のあり方を大きく捉まえてみよう。
2)生活の担い手(個人)や生活単位としての世帯がどうなっているか?
3)生活の場としての地域社会の様子はどうなっているか?
4)個人や家族の働き方はどうなっているか?
5)生活時間から見ると今の生活はちょっと変だな。
6)地域社会などでの生活インフラの整備はどうなっているか。
7)企業や地域社会などでの生活支援の制度はどうなっているか。
8)『豊かなアジア 貧しい日本』?→自然環境に打撃的な生活様式に未来はある?
9)私たちの生活価値を見直してみよう。
2.生活をとらえるための常識の非常識
1)「豊かな社会」は自明か?
2)「貧しい社会」は貧しいか?
3)生活の「豊かさ」度を測る-ビル・ゲイツと私?
4)アメリカ式生活様式とトイレ-生活文化のとらえ方
5)男と女、親と子ども-関係としての生活
6)ムラとマチの生活空間
7)“24時間闘えますか!”-時間としての生活-
3.生活把握のための基本的枠組
1)生活と生活過程
2)生活の単位
3)現代における生活の基礎単位の動揺と生活単位の社会化
4)生活単位の「社会化」
5)資本主義経済社会における生産過程と消費過程
6)生活文化の形成と家族
Ⅱ.現代日本の生活分析
1.現代日本の日本は「ゆたかな国」か?
1)何故このような問いかけが福祉労働者に必要なのか?
2)「ゆたかな国」と「ゆたかな生活」の幻惑の社会的意味→「ゆたかな社会」=「ゆたかな生活」論が見落とし、切り捨てているものは何か。
3)生活の格差は広がっているのに何故「ゆたか」に見えてしまうのか?
4)これまでの「ゆたかな」生活論は生活論は生活の長期的・総合的生活を無視
5)企業社会の解体と貧困・生活不安の拡大
2.生活をとりまく大状況-「生活不安の時代」の到来?
1)時代の転換点を示すできごと
2)こうした困難や不安の背後にあるのは何か
3.勤労者生活の困窮化と家族の危機
1)総務庁「家計調査」
2)現代の勤労者家計構造は何を示しているか
4.社会保障「構造改革」による生活危機の促進
1)90年代の社会保障「構造改革」
2)社会保障「構造改革」の名で何が行われてきたか?
3)なぜ、社会福祉基礎構造改革か?
5.真のゆたかさを保障するものは何か-阪神・淡路大震災が問いかけるもの
1)現代の生活様式と社会保障
2)社会保障を拡充することの社会・経済的意味
3)阪神・淡路大震災が明らかにしたもの
総合社会福祉研究所 |